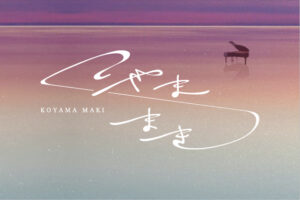2014.06.05「宵待草」大正時代の名曲を弾いてみた
最近、高齢者の音楽回想療法の講師をするようになって、昔の曲を
たくさん聞くようになりました。
昔、古臭い、つまらないと思ってあまり気にしてこなかった戦前戦後の曲ですが、
中には素晴らしいものが沢山あることがわかりました。
まずは詞がすばらしい。 戦争という大きな暗い残酷な時代に生きる人々の
胸を打った曲は、美しくてせつなくて、中身が深い。
この年になってその詞を味わえるようになりました。
もう一つのメロディも、また素晴らしいものがあります。
今日取り上げたのは、「宵待草」大正7年(1918年)、今から約100年も前の作品。
夏の宵に咲き、朝はしぼんでしまう、月見草の一種。
竹下夢二が自身の失恋から作り上げた曲らしいが、エピソードを読むと
かなり恋多き男性だったようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/宵待草
音楽的にいうと、当時は単純なコード進行だったと思いますが、このメロディーが
なんとも雰囲気がいいのです。
現代になって西洋の和音とその展開の知識を持てば、
いかようにもバリエーションが生まれるメロディーです。
100年前の作曲家の多忠亮さん、すごいなと思います。